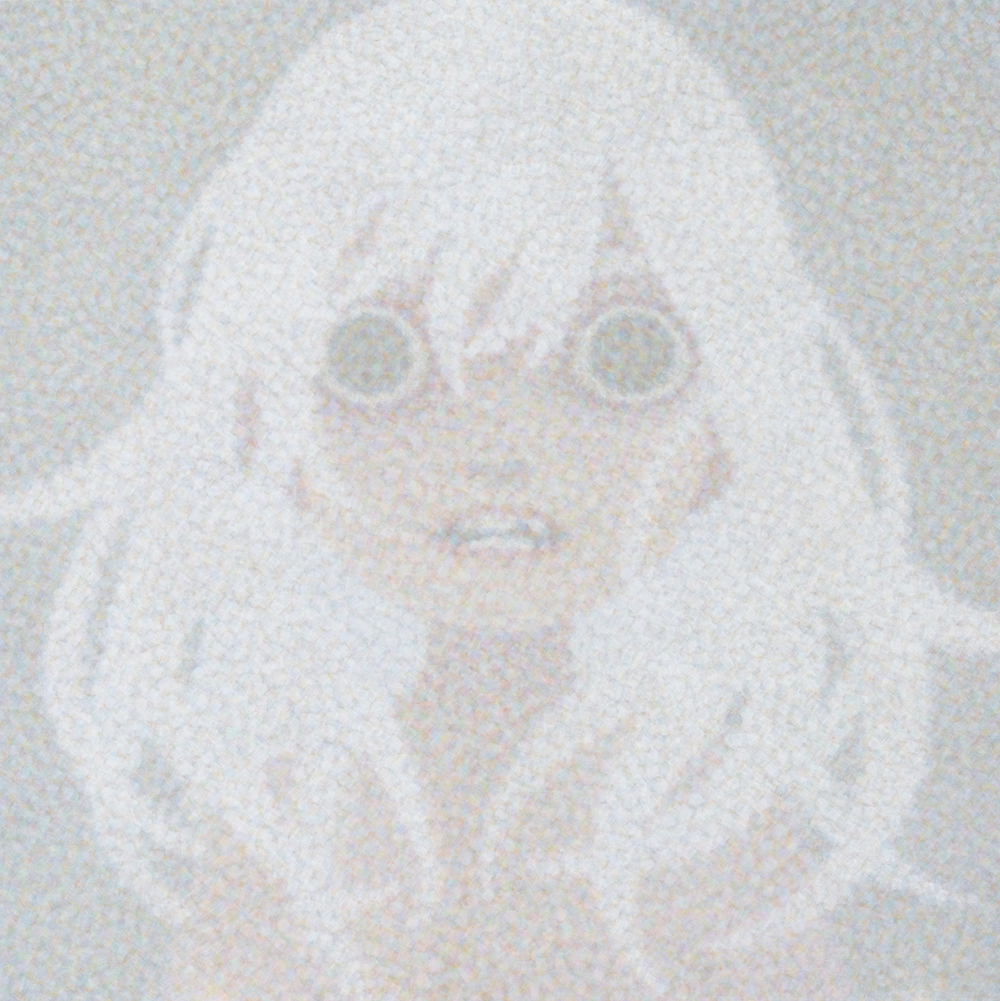|
■ Even These Stones Will Cry Out -マーティン・ホナサン個展-
■ 出品作家 マーティン・ホナサン
■ 会 期 2016年9月17日(土) ~ 10月1日(土)
閉廊日:日・月曜日、開廊時間:12:00~19:00
■ 会 場 YOD Gallery
530-0047 大阪市北区西天満4-9-15 TEL/FAX 06-6364-0775
www.yodgallery.com
info@yodgallery.com
■ 9月17日(土)18:00~ レセプションパーティー
YOD Galleryにて
■ お問い合わせ
YOD Gallery
530-0047 大阪市北区西天満4-9-15 TEL/FAX 06-6364-0775
E-mail:info@yodgallery.com
※画像データなどご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
□ 趣旨
このたびYOD Galleryでは、フィリピンにて注目の現代作家マーティン・ホナサン(Martin Honasan, b1976 ケソン市、フィリピン)の日本初個展「Even These Stones Will Cry Out」を開催いたします。ホナサンはゲシュタルトやパレイドリアといった心理学的観点から、顔に焦点を当て抽象的な肖像画を生み出す作家です。彼の作品では絵具やキャンバスといった画材と人物の顔が構成要素として同等に扱われ、鑑賞者の視覚と心が生み出す像を通して倫理観、精神性、存在と意味を問いかけます。
2016年6月、ホナサンは寝屋川市のYODレジデンス滞在作家として一ヶ月間家族と大阪で過ごし、制作を行いました。大阪での生活は彼自身、またその作品にどのような影響を与えたのでしょうか。是非この機会にご高覧賜りますよう、お願い申し上げます。
アーティストステートメント
大阪府寝屋川市昭栄町に着いた時、すぐにその複雑さを感じ取った。同時にどこか無理のないシンプルさがある。どの国へ行っても最初に気づくのはその地の質感だ。-- 土地と、その上に繁栄する構造体。街のレイアウトと交通の流れを見れば、大体のシステムの重なりと配置、そして人々の感性を知ることが出来る。大阪ではバラエティに富んだ地元の人々に会った:身なりの良いビジネスマン、赤ん坊と出かける女性、生き生きした老人達。---ほとんどがママチャリと呼ばれる日常使いの自転車に乗っている。「ママの自転車」という意味らしい。外から来た者として、何代にもかけて磨き上げられある種の穏やかさと洗練を生み出した、一つの歴史の重なりに驚かされた。
今回の滞在中、友人の日本人が淀屋橋中心部にある寺院に連れて行ってくれた。大阪府の中ではより活発な街だ。彼はここにきて静かな時を過ごし、また成功を祈るという。「崇拝」という概念について考えてみた。崇拝は大抵の場合寺院や祭司、そして儀式と結びつけられる。私自身は何かを崇拝する人自身が寺院となり、そういった人が集まり教会となる--崇拝とは個人が最も価値を置く存在に対し捧げるものだと信じている。多くの場合、人々は全て寺院であり、我々は自らが最も価値を置くものを中心として生活を築いていく。崇拝の対象となるものは、崇拝者自身のアイデンティティの中心部にあり、また賛美の中心となる。
今回の作品群に描くのは、人間の衝動において最も一般的なものである崇拝、そしてそれがどのように我々のアイデンティティを構成するかについてのメタファー(暗喩)だ。私の作品はダメージから始まる。作業空間から回収されたカンヴァス小片のうち、ほぼ全てがリサイクルされ、次の作品に加わり、そして次のかけらを生み出す。私は今回も小片を寝屋川市に持ちこみ、大阪で新たに購入した素材を混ぜた。新しいカンヴァスと古いペインティングの一部にナイフと裁ちばさみで穴をあけ、切り、引き裂く。生まれてきた小片を折り重ね、しわくちゃにし、新たな面にコラージュする。コラージュは無作為なストロークにより彩色され、ストロークは広範囲のものから徐々に細く、繊細な動きへと変化し、人の顔として認識可能な部分が現れるまで続く。
我々は、感情を最も即時に、また内面を表す道具として顔を用いる。本作品シリーズでは自身や身近な人々の顔のパーツを素材として用い、崇拝の親密性(誠実さ)と私たちの経験を伝えたい。
イエスがオリーブ山の下り坂にさしかかられたとき、弟子の群れはこぞって、自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。「主の名によって来られる方、王に、祝福があるように。天には平和、いと高きところには栄光。」すると、ファリサイ派のある人々が、群衆の中からイエスに向かって、「先生、お弟子たちを叱ってください」と言った。イエスはお答えになった。「言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫びだす。」 (ルカ19:37-40)
展覧会タイトル「Even These Stones Will Cry Out」は直訳すると「石ですら叫びだす」という意味で、聖書「ルカの福音」の一部を元にしたものだ。パリサイ人がイエスの弟子たちを黙らせようとしたとき、イエスはこの世の全ては神を崇めるために創られたと答えた。本展の作品群は人間の衝動的崇拝に対する熟考であると同時に個人のアイデンティティを明らかにする崇拝、祈り、そしてその他信仰に関する行為のメタファーとなっている。
― マーティン・ホナサン
□ マーティン・ホナサン(Martin Honasan)プロフィール
マーティン・ホナサン(Martin Honasan, b1976 ケソン市、フィリピン)はアテネオ・デ・マニラ大学学際科学科にて学位を取得(心理学&コミュニケーションアート専攻)。画家業に専念する前は作品制作の傍ら広告アートディレクターや(1999-2001)、自身のデザイン会社役員も務めていました(2001-2004)。ホナサンはフィリピンを中心に活動し、アクリルと水彩絵の具による絵画を主なスタイルとしています。2005年以降フィリピン、香港、日本と様々なグループ展に参加、個展も開催してきました。またArt Fair Philippines、Art in the Park、Bazaar Art Jakarta、Manila Artといった国内外のアートフェアにも参加しています。個展は2011年より継続的に開かれ、開催場所には2015年のフィリピン文化センターも含まれます。この度YOD Galleryでの個展が10回目となります。
[主な個展・グループ展]
2016 Art Fair Philippines, YOD Gallery X Kogure, Art Verité, West Gallery The Link,
Parkway Drive, Ayala Center, Makati City, Feb. 18 - 21
2015 An Other (solo exhibit), Vinyl on Vinyl, 2F warehouse 2, 2135 Chino Roces Ave.,
Makati City, Oct 21
Shadows of Things to Come (solo exhibit), Boston Art Gallery,
72 Boston Street, Cubao, Quezon City, Oct. 10
Everything is Created Twice, Cultural Center of the Philippines,
Main Theatre Building, Roxas Blvd., Pasay City,
May 14 - June 14
Art in the Park, Art Verité, Boston Gallery, Vinyl on Vinyl, Makati City, March 22
Art Fair Philippines, CANVAS, The Link, Parkway Drive, Ayala Center, Makati City,
Feb. 5 - 8
2014 Alay 17 (group show), Boston Art Gallery, 72 Boston Street, Cubao, Quezon City,
Dec. 7 - 21
Extended Play (inaugural group show), Vinyl on Vinyl, 2F warehouse 2,
2135 Chino Roces Ave., Makati City, Aug 27
2014 Soil (6th solo exhibit), Boston Gallery, 72 Boston St, Cubao,
Quezon City, Aug 23 - Sept. 8
Filipino Myths &Legends, Center for Art, New Ventures, & Sustainable
Development, U.P.Vargas Museum, June 17 - July 15
Asia Art Contemporary, Floren Gallery, Conrad Hotel, Hong Kong, May 15 - 18
Art in the Park, Art Verité, Boston Gallery, Vinyl on Vinyl, Makati City, March 23
Singularity (5th solo show), Art Galileia, Fort Pointe Building, BGC, Taguig, Feb. 28
- March 14
2013 Alay 16 (group show), Boston Art Gallery, 72 Boston Street, Cubao,
Quezon City, Dec. 7 - 21
Everything The Same Way (group show), Ysobel Art Gallery, BGC, Taguig, Nov. 28
- Dec. 11
Zoology of a Concrete Jungle (group show), Gallery Orange, Bacolod City, Sept. 7
- 30
The Weight of Glory (4th solo exhibit), NOW Gallery, EcoPlaza Bldg., Makati City,
Sept. 4 - Sept. 17
Love Stories (group show), Galería Paloma, July - August
The Night Nebula (group show), Paseo Gallery, A.R.T. Center,
Megamall,Mandaluyong City, July 10 - 24
The Human Hide (3rd solo exhibit), The Crucible Gallery, Megamall,
Mandaluyong City, July 2-14
Art Fair Philippines, Paseo Gallery, The Link, Parkway Drive, Ayala Center,
Makati City, Feb. 7-10
2012 Then We Shall See (2nd Solo Show), Ysobel Art Gallery, Serendra, BGC, Taguig,
May 21-June 9
Pure Imagination (group show), Altromondo, Greenbelt 5, Makati City,
Sept. 4 - 14
After Caravaggio (group show), NOW Gallery, EcoPlaza Building, Makati City, Aug. 4
- Sept. 1
2011 Digging In The Dirt (a solo exhibit), Yellow Door Gallery, Power Plant Mall,
Rockwell October 7-22
Manilart '11, Artes Orientes Gallery, NBC Tent, Bonifacio Global City,
Taguig, July 16-19
Ten, (group show), Ysobel Art Gallery, Serendra, BGC, Taguig, May 21-June 9
2010 Phases (group show), Yellow Door Gallery, Power Plant Mall, Rockwell, Sept.25
2009 Manilart '09, Quattrocento Gallery, NBC Tent, Bonifacio Global City, Taguig,
16-19
|